|
名前 |
内容 |
| あい |
東金城(アイカナンキャ)家
 |
 |
1905(明治38)年に建てられた、竹富島で現存最古の瓦葺き民家であるアンカナンキャ(東金城)さん宅です。2方向の屋根にシーサーが乗っています。
映画「ニライカナイからの手紙」で、主人公の安里風希と安里尚栄が住む家としてロケ撮影もされました。
なお、2012(平成24)年秋から改修が行なわれ2013年3月に完成しました。仲筋集落内の西側に位置しています。 |
| あい |
アイヌソイ(東のソイ)*
 |
 |
美崎御嶽の北側の海岸の約50m沖合にある、東側の岩です。ちょうどガンギ(桟橋)跡の沖合になります。西側にはインヌソイ(西のソイ)があり、竹富島にはこの2つの島に住む、結婚を逃したネズミの民話(伝説)が残されています。
民話によると、東の岩の男ネズミが、付近に住む大魚を介して西の岩の女ネズミと婚約しました。その仲介のお礼が小魚の料理でした。ところが他の小魚たちが「ネズミのために同じ魚を犠牲にするのは困る」と大魚を叱責しました。このため仲介の大魚は去り、ネズミは西の岩に渡れず結婚も成立しませんでした。そのため互いに岩の上から眺めて悲しんだそうです。 |
| あい |
あいのた会館
 |
1995(平成7)年の4月に建設された、東集落の集会所(会館)が「あいのた会館」です。
竹富島ではこのほかに、西集落には「いんのた会館」、仲筋集落には「羽山会館」があります。 |
| あい |
アイヤル浜
 |
蝶を紹介した看板
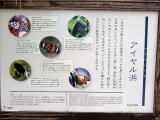 |
郵便局の筋を東南へ東集落、仲筋集落、外周道路を越え、自転車で15分くらいの所にあるビーチ。途中の小道では各種の花に色々な蝶が舞っています。遠いせいか人も疎らで比較的静かに過ごすことができます。遠くに高速船の往来が眺められます。潮の流れが速いため遊泳は禁止されています。ここでも星砂を見ることができます。 |
| あか |
あか山丘
 |
竹富島の中心付近にある小高い丘で、竹富島全体を見渡すことができます。
観光ポスターでよく見られる赤瓦の街並みは、この丘にある「なごみの塔」より撮影されたものです。
|
| あか |
赤山王の墓*
 |
赤山王の墓は、島北部を南北に縦断するミシャシ道と、東桟橋からカイジ浜間の外周道路の交差点から約70mほど東へ向かった北側の茂みの中にあります。
赤山王は平家の落武者で、1185年、壇ノ浦の合戦で敗れ落ち延び、流れ着いたのが竹富島の北端の美崎(ミシャシ)との言い伝えがあります。赤山王はその後、村人とも親しくなりました。島の中央にある「なごみの塔」のある赤山丘は、赤山王が居城した跡だと言われています。
現在、赤山王の大祭として、毎年10月11日と2月11日に親戚縁者が集い、赤山王の遺徳を忍んでおられるそうです。石積みの前の墓碑は、上勢頭亨氏(日本最南端の寺である喜宝院の住職)によって据えられました。 |
| あさ |
安里屋クヤマのお墓
 |
お墓に行く途中の道
 |
琉球民謡「安里屋(あさどや)ユンタ」で歌われる竹富島に生まれた絶世の美女、安里屋クヤマのお墓です。
「安里屋ユンタ」は、役人から無理な求愛を断った絶世の美女・安里屋クヤマのエピソードを唄ったもので、琉球王朝時代の庶民の心情が伝わるものです。
西桟橋の北側で周回道路(小道)から少し海側に下った所にあります。お墓なので周囲では静かにすごすようにしましょう。 |
| あさ |
安里屋クヤマ生誕の地*
 |
「サー君は野中のいばらの花か サーユイユイ 暮れて帰れば やれほに引き止める またハーリヌ ツィンダラ カヌシャマヨ」の安里屋ユンタで有名な、絶世の美女と言われた安里屋クヤマの生誕の地は、なごみの塔の南南西方向、西集落(インノタ)にあります。
クヤマは1722年に同地に生まれ、1799年に当時としては長寿の78歳で没しました。クヤマが16歳の時、地割り制度を施行するため琉球王府から役人が来島しました。島で役人の給仕を探した結果、クヤマが選ばれました。その時、目差(助役)が与人(村長)を差し置いてクヤマに声を掛けたものの、ひじ鉄をくわされたと民謡「安里屋節」で歌われています。 |
| あー |
アーバー石*
 |
北海岸の美崎(ミシャシ)に伝わる石化伝説のアーパー(老婆)石です。別名、アバーインとも呼ばれる老婆の姿に似た石です。竹富島の人々は立ち神(タチンガン)と呼び、海の守り女神として尊び信仰されておられるそうでする。
その昔、新里村に美しい娘がいました。しかし、娘は仕事もせずフータバ娘(怠け者)と呼ばれました。ある日、母親が美崎の海岸でアオサを採るため娘を連れ出しました。ところが急に潮が満ちて娘をのみ込むと、たちまち老婆になり石と化しました。
なお、この石の沖合にはアイヌソイ・イルノソイがあり、東隣にはガンギ(桟橋)跡があります。 |
| いる |
イルヌソイ(西のソイ)
 |
美崎御嶽の北側の海岸の沖合にある岩で、ガンギ(桟橋)跡の西の沖合になります。
アイヌソイとともに、竹富島にはこの2つの島に住むネズミの結婚の民話(伝説)が残されています。
[アンヌソイの項を参照]
|
| いん |
いんのた会館

|
「西集落」の集会所が、「いんのた会館」です。
1984(昭和59)年7月に建設されました。 |
| えと |
干支の神々
 |
 |
喜宝院蒐集館の入り口にある、サンゴ石の自然形状を干支に見立てて、その順に並べたものです。結構、似ています。 |
| おね |
お願いシーサー
 |
これは「お願いシーサー(別名:お祈りシーサー)」という、手を合わせてお願いしているシーサーです。
どこにあるのかを誰にも聞かずに探し出し、お祈りをとなえると一つだけ願い事が叶うそうです。
でも、他人からその場所を聞いたら効き目はなくなるそうですから、自分の力だけで探し出してください。
意外と気付かないでここを通り過ぎているかもしれませんよ。 |
| かい |
カイジ浜
 |
野良?猫
 |
島の西側で、コンドイビーチの南側に位置する比較的、小規模のビーチ。別名「星砂の浜」と呼ばれシーズンを問わず観光客で賑わっています。潮の流れが速いので泳ぐのにはあまり適しませんが、「ハスノハギリ」の大きな木陰がありのんびりと過ごすのにはよい場所です。小さな土産物屋もあり色々なアクセサリー等を売っています。野良?猫がたくさんいることでも有名。竹富島に着くと、まず最初にここの猫の様子を確認するのが最近の私の行動パターンです。 |
| がそ |
ガソリンスタンド
 |
竹富島唯一のガソリンスタンド:竹富(ゆがふ)石油です。
日本最南端のお寺として知られる喜宝院蒐集館の前の道を西に進むとあります。
営業は平日の13:00~13:30の30分間です。 |
| がん |
ガンギ跡

|
島の最北部にある美崎(ミシャシ)海岸は、かつて島の主要な港として大正年間頃まで使用されていました。
今も当時のガンギ(桟橋)跡を見ることができます。 |
| きほ |
喜宝院蒐集館*
 |
(キホウインシュウシュウカン)
 |
蒐集館は、日本最南端のお寺・喜宝院に併設する八重山の民俗資料を展示した博物館です。
先代住職の故・上勢頭亨氏が生涯をかけて収集した約4000点を収蔵、展示しています。そのうちの842点が2008年、沖縄県第1号の「国登録有形民俗文化財」として登録されました。
収蔵品はほとんどが竹富島で収集されたもので、民具や染織、焼き物、葬礼、通貨など多岐にわたりますが、中でも人頭税関係史料は、藁算(ワラサン)、刑罰道具、文書など貴重なものが数多くあります。 |
| きゅ |
給水タンク*
 |
 |
竹富小中学校グランド西側に移設されている給水タンクです。1971(昭和46)年、3月から9月までの191日間の異常干ばつが八重山を襲い、竹富町の各離島は飲料水が底をつきました。竹富小中学校の給食も6月半ばで中止されました。このような状況に対し、八重山干害対策協議会が日本政府派遣の干害調査団へ「飲料水緊急対策施設の計画」を含む請願で完成させたのがこの給水タンクです。校舎新築に伴い現在地に移設されたのは「竹富島憲章」の保全優先の理念によるものです。 |
| きゅ |
旧与那国家*
 |
「グック」
 |
旧与那国家は、1913(大正2)年の建築で、2008年に指定された、国内最西端の国の重要文化財建造物です。「フーヤ」と呼ばれる木造平屋の主屋と、台所仕事を行うための別棟「トーラ」から構成されており、竹富島の住居形態と生活様態を理解するうえで、高い価値があるとされています。「フーヤ」の正面には石積の「マイヤシ(ヒンプン)」があり、宅地周囲は「グック」と呼ばれる石垣に囲まれており、竹富島伝統的建造物群保存地区の核となる住宅とされています。
この旧与那国家住宅は、竹富島の東集落(竹富小中学校の東側)にあります。 |
| くす |
小城盛(クスクムリ)
 |
世持御嶽の裏側にある石垣の火番盛跡。ここでは昔、付近の海上を行く貢船や異国船を監視し、何か起こった際には石垣島の蔵元に通報するために狼煙を上げたといわれています。火番盛は同じように他の島々にもあり、例えば黒島にはプズマリ、波照間島にはコート盛、与那国島にはダティクチディがあります。 |
| くら |
蔵元跡の碑*

|
蔵元跡
 |
カイジ浜に下りる坂の左側にある遺跡。蔵元は、1524年に琉球王朝時代に王府が竹富町出身の西塘を竹富首里大屋子(タケトミシュリオオヤシ)に任命し、八重山を統一するために創設した政庁(役所)の跡です。
その後、竹富島は土地が狭く、交通の便も悪く、政庁の場としては不便なため、1543(天文12)年に石垣島の大川に移設されました。竹富島での蔵元は、20年間続いたこともあり約200坪の屋敷跡や、高さ1.5m程の野面積みの石垣が東と南に現在でも残っています。また北側のヤブには鍛冶屋跡もあります。八重山の貴重な旧跡です。1959(昭和34)年に、沖縄県指定文化財(史跡)となりました。 |
| こぼ |
こぼし文庫*
 |
竹富島をこよなく愛した京都の随筆家の故・岡部伊都子さんが、島の子供たちへと、復帰記念日の1972年5月15日に蔵書とともに建物(赤瓦の民家)まで寄贈された文庫です。これを機に島をあげての本格的な読書サポート活動がスタートしました。
当時、島内には図書館もなく本屋もなく、本1冊を買うにも借りるにも石垣島まで出かけなければならない状況でした。子供たちは「こぼし文庫」の本を通じて「読む力・書く力・見る力」を育んでいます。1980年には「こぼし子供会」が発足し、毎週日曜日を定期活動日として、本の整理や清掃、読書、発表などが行なわれています。 |
| こん |
コンドイビーチ
 |
コンドイビーチ
 |
別名「潮がれ浜」。島の西側に位置する、遠浅で波も穏やかで安心して海水浴が楽しめるビーチ。白砂と海の色とのコントラストが美しく、向かいに西表島がよく見えます。島の中心地から少し距離が有るため自転車での移動をお勧めします。但し、歩いていけない距離ではありません。東屋もあり、のんびりと本を読んだり、シュノーケリングしたり、思う存分自分なりの時間を過ごすことが出来ます。夏場は相当に混雑します。シャワーやトイレ等の施設も完備され、サンセットスポットとしても有名です。竹富島に行けば誰もが訪れる観光スポットです。 |
| さき |
崎山毅先生の記念碑
 |
 |
竹富島を愛し、竹富島民のための医療活動に従事された八重山保健所所長・崎山毅先生の記念碑です。
「波照間屋敷」敷地内に建立されています。 |
| しー |
シーサー
 |
 |
竹富島の家々の屋根の上にはシーサーが乗っかっています。それぞれに格好や表情が異なっていて、色々な名前がつけられています。
屋根上に設置されたシーサーの詳細については、こちらを参照してください。 |
| しゅ |
酒造所跡の碑
 |
竹富島小中学校の校門近くにある「酒造所跡」の碑です。現在、島内での酒造は行われていません。 |
| しん |
新里村遺跡
 |
 |
新里村遺跡は、集落の北側(小城盛や世持御嶽の北側)にあります。
新里村遺跡は「花城井戸」という井戸を中心にして、その東側と西側に広がる集落遺跡で竹富島の集落の発祥の地といわれています。昭和61年度・62年度に沖縄県教育委員会により発掘調査が実施され、遺跡からは大量の土器をはじめ、中国製陶磁器(白磁碗、青磁碗、褐釉陶器)、須恵器、鉄鍋、鉄製のヘラ、刀子(小刀)が出土しています。これらの出土遺物から井戸の東側は12世紀末~13世紀、西側は14世紀に形成された集落であることが明らかになりました。井戸の西側、14世紀の集落には石積みが残っており、その石垣で囲まれた各屋敷と屋敷は通用門(出入口)で結ばれていて現在の集落とは異なった形態をなしています。 |
| すい |
水牛車
 |
竹富島観光の名物でもある水牛車は、集落をのんびりゆっくり巡ります。
ガイドさんのお話と歌に耳を傾けながら、昔ながらの風情を残す町並みを30分程度かけて廻ります。
水牛車運営会社は、民宿新田荘が運営する新田観光と、竹富観光センターの2社があります。水牛車観光は両社とも似たような内容ですが、廻るルートは異なります。(すごく大雑把な言い方をしますと、なごみの塔の西側(安里屋クマヤの生家など)を廻るのが新田観光で、東側(まちなみ館周辺など)を廻るのが竹富観光センターです。)
※ 以下の情報は各社のHP等から引用したものです。(2021.11.20現在) 利用時には再確認願います。
ともに竹富港からの無料送迎バスがあります。
【新田観光】
・大人(中学生以上) 1500円
小人(小学生以下) 750円
未就学児は大人の膝の上なら無料
・所要時間約30分
・電話にて事前予約可能(当日予約でも可)
・毎週水曜定休日(祝日を除く)、種子取祭の三日間休業、その他悪天候時に臨時休業あり。
【竹富観光センター】
・大人(中学生以上) 2000円
小人(3歳~小学生) 1000円
幼児(0~2歳児) 無料
・所要時間約25分
・事前予約不要
※ 定休日:種子取祭の2日間、その他悪天候時に臨時休業あり。 |
| すい |
水道記念碑

|
水道記念碑は、竹富小中学校の南側にある仲筋井戸(ナージカー)の南側向かいにあります。
竹富島は隆起珊瑚礁の島で、山も川もないため水資源に乏しく、古くから水には困窮していたようで、島の人々は、天水の溜め置き、あるいは浅い井戸を頼りに生活用水を得ていました。旱魃の時には水を確保するために船で石垣島や西表島まで行って運んでくるという苦労が続いていました。
1976(昭和51)年、 政府と石垣市の了承を得て、石垣浄水場の上水を海底送水管により竹富島に運ぶ水道が敷設されました。この石碑は、その事業の完成を顕彰するために竹富町が建立したものです。 |
| すん |
西のスンマシャー*
 |
東のスンマシャー*
 |
スンマシャーは、集落の入口に巨木を植え、それを取り囲むように石垣を積み回したものです。石垣方言ではチィンマーセーと呼びます。
風水思想に基づく集落作りの一つで、病魔や凶事が集落に進入するのを遮るため、道路を曲げたりY字型にしてその勢いを弱める目的もあります。またここからが生活の場という目印でもあります。 |
| せき |
石馬 (北側より)
 |
同 (南側より)
 |
赤山丘・なごみの塔の敷地内(東側)にあります。 |
| たい |
太鼓石
 |
太鼓石は、「赤山公園」にある「なごみの塔」の敷地内(南側)にあり、石を当てると太鼓のような音がすることから名付けられています。 |
| たけ |
竹富島高架配水池*
 |
仲筋集落近く、製糖原の豊見親城(トゥールングック)に隣接する容量90tの高架配水池、いわゆる給水塔です。
この配水池は石垣市からの海底送水事業として1976(昭和51)年10月に完成しました。
仲筋集落入口、ナージカーの前には水道記念碑が建てられており、そこには「(前略)於茂登の真水を引き恩恵に浴したことは聖代の一大快挙であり(中略)永遠に島の発展の礎となることを祈念する」と記されています。 |
| たけ |
竹富小中学校 校門
 |
校舎
 |
ここは、かつて大多月乃・津田寛治・勝野洋・モーニング娘らが出演し、2004年に公開された映画「星砂の島、私の島 ~アイランド・ドリーミン~」のロケ地でもあります。
校門は、いつも花で一杯の美しい学校です。 |
| たけ |
竹富島まちなみ館
 |
竹富島のいわば公民館。まちなみ保存地区の景観に配慮して、伝統的な民家の主屋(フウヤ)と別棟(トウラ)が連なる造りを大きくした構造で、研修室、舞台・交流スペース、展示スペースがあります。建物は、東南アジア産などのオガタマノキ(方言名ドゥスヌ)の大木を使い、木に穴を開けてつなぐ組み方がされています。壁は中国産御影石、屋根は赤瓦ぶき。周囲の石垣積みは島民が総出で取り組み作られました。 |
| たけ |
竹富の歌碑
 |
喜宝院蒐集館の向かい、水牛車の「新田観光」の敷地の隅にある歌碑です。
「かしくさや うつぐみど まさる」
と記されています。 |
| たけ |
竹富東港
 |
竹富島の玄関。2004年に現在の浮き桟橋となりました。
船の先端部(舳先)と岸壁の間で乗降していた頃からすると、格段に便利になりました。 |
| たけ |
竹富民芸館
 |
伝統芸能を正しく受継ぎ発展させていくための仕事場として、島の人々によって運営されているのがこの竹富民芸館です。竹富島の代表的な織物で、約300年の歴史を持つミンサーをはじめ、八重山上布、芭蕉布などを織る作業を見学することができます。館内では織物が出来上がるまでの製造工程を詳しく紹介したパネルも展示しています。また、講習会や展示会が行なわれることもあり、ミンサー帯や財布など、ここで織られた作品の販売もしています。入場は無料。 |
| たけ |
竹富郵便局
 |
郵政公社のコマーシャルにも出ていた竹富郵便局です。島唯一の金融機関です。ATMも利用可能ですが、日曜日は閉まっています。屋根のシーサーが可愛いですよ。 |
| ちろ |
ちろりん村
 |
旧ちろりん村
 |
2012年8月28日から同年10月16日まで、NHKのドラマ10で放送された『つるかめ助産院~南の島から~』のなかで、「パーラーハジメ」として紹介されていたお店です。2013年夏に全面改装され、かつての「パーラーハジメ」の頃に描かれていた外壁の絵は全てなくなりました。 |
| つる |
つるかめ助産院 ロケ民家
 |
同 玄関
 |
NHKのTVドラマ「つるかめ助産院」の撮影が行なわれた民家です。
この家は、竹富島の他の一般的な民家とはちょっと雰囲気が違っていますが、かつて石垣島にあった病院(医院?)を移設したものだそうです。
この写真では玄関の右側に「つるかめ助産院」と看板が掛かっていますが、当然のことながら、現在、この看板は外されています。 |
| てぇ |
てぇどぅんかりゆし館
売店
 |
同左
待合室
 |
「てぇどぅんかりゆし館」は竹富港(東港)の船客待合所で、2003年に完成しました。
クーラー付の待合室、お土産屋さん、総合案内所NPOたぃどぅんなどがあります。
「てぇどぅん」とは竹富島の地元での呼び名、「かりゆし」とは旅人の航海の安全を祈るという意味です。
なお以前の屋根付き歩道とトイレの待合所は2012年春に解体され、今はその姿を見ることはできません。 |
| てん |
天使の小道
|
 |
竹富島の白砂の道も、今ではほとんどの道が拡張されましたが、唯一、昔ながらの小道が残されている場所があります。それがこの「天使の小道」と呼ばれている道です。
安里屋クヤマの生家の北側(裏側)にあります。 |
| とぅ |
トゥンドバルの畑
 |
 |
安里屋ユンタで謡われるヒロインの安里屋クヤマが与人から授かったという畑です。島きってのいい土地だったようです。できた野菜・果物は時々無人販売されています。
旧与那国家の東側にあります。 |
| なー |
ナーラサ浜
 |
ナーラサ浜紹介看板
 |
島の東に位置しており、丁度、コンドイビーチとは反対側にある浜。道が悪く遠いため、人も少なくのんびり過ごすことができます。アイヤル浜からも歩いて行くことができます。
集落の道に撒かれている白砂はナーラサ浜の少し先(写真少し奥)のキトッチ浜の砂が最も適していると言われています。
なお、この浜でも星砂を見ることができます。 |
| なか |
仲筋井戸(ナージカー)*
 |
井戸内
 |
竹富島のほぼ中央、仲筋集落の上り坂北口に位置します。1976(昭和51)年に石垣島からの海底送水が実現するまで、貴重な生活用水として使われていました。
仲筋井戸はその昔、仲筋村の村建ての神・アラシハナカサナリの飼っている犬が、干ばつにも関わらず尾が濡れているのに気付いた飼い主が不思議に思い、後をつけて掘り当てた井戸と言う言い伝えがあり、犬の形に掘ってあるといわれています。竹富島の中で最も水量が豊富な井戸として長い間島民の生活を支えてきた井戸です。今では、元旦や出産祝い時にこの水を使用しているそうです。 |
| なか |
仲筋のヌベマの水がめ*

|
水がめのある幸本家
 |
その昔、新城島で焼かれていたパナリ焼きの水がめと苧麻の種子を得るために、仲筋村の幸本家で大事に育てられていた一人娘のヌベマという娘が新城島に嫁ぐことになったという言い伝えのある水がめです。水がめは雍正12年(西暦1735年)に作られ、この水がめが幸本家に寄贈された際にヌベマは13歳だったそうです。
1991(平成3)年に竹富町指定文化財(工芸品)に指定されました。 |
| なご |
なごみの塔*
 |
塔からの赤瓦の街並み
 |
西集落の中心に位置する赤山公園(赤山の丘:平家の落人伝説がある丘)にそびえ立つ高さ4.5mの鉄筋コンクリート造りの塔。1953年の公園整備に伴って建てられました。頂上からだと海抜は22mになります。かなりの急傾斜ですが、ここからの眺めは、沖縄の原風景を目の当たりにすることができます。そしてここは、竹富島の赤瓦の街並みが一望できる唯一の場所です。竹富島を紹介する多くのガイドブックやツアーパンフレットにはここから撮影された写真が使われています。昼間は多くの観光客のため登るのに順番待ちをしなければならないこともありますが、夜は南国の星空を独り占めできます。国の登録有形文化財に登録されています。
階段の幅が狭く、勾配が急ですので、上り下りには十分注意して下さい。
※ 2016.9.17より塔の老朽化等のため昇り降りが禁止されています。 |
| にー |
ニーラン石*
 |
西桟橋とコンドイビーチの、ほぼ中間の波打ち際にそびえる立石です。「ニーラン」とは、はるか彼方の神の国を意味し、この場所は神を迎え入れる場所(目印)で、その昔から、ニーランから船でやってきた神がこの石にとも綱を結びつけると言われています。
毎年旧暦の8月8日には早朝から神司(カンツカサ)や村の役員がこの場に集い、供え物をしてドラや太鼓を打ち鳴らし、トンチャマーを歌いながら、手招きをしてニライカナイからの神船を迎える「世迎い(神々が世に訪れて五穀豊穣や世(幸)をもたらしてくれる)」の行事が行われます。 |
| にし |
西桟橋
 |
集落の中心から西に向かって行けば辿り着く情緒溢れる古い桟橋。その昔、ここから対岸の西表島に農耕に出かけていました。夕日を眺めるには絶好のポイントで、夕方ともなると宿泊の観光客で賑わいます。干潮の時は、西桟橋~コンドイビーチ~カイジ浜と浜辺を歩くことも出来ます。国の有形文化財に登録されています。 |
| にし |
西塘御嶽*
 |
竹富島が生んだ偉人、西塘が祀られています。
西塘は視察で訪れた王府・中山軍の大里親方に伴われて首里に行き、首里王府に25年間仕えた技師で、1519年首里の園比屋武御嶽の石門築造や首里城北面の城壁設計役などで活躍しました。1524年、竹富首里大屋子という頭職に任ぜられ八重山諸島の統治にあたりました。帰島した西塘はカイジ浜に蔵元を設置し、八重山を統治しました。この御嶽は彼の屋敷跡であるとともに、埋葬地でもあるといわれています。村人は統治者までのぼりつめた偉人を御嶽の神と祀り、信仰を深めるようになりました。 |
| にん |
人頭税廃止百年記念之碑*
 |
八重山人頭税廃止百年記念事業期成会によって、仲筋集落入口のンブフルの丘の下に、2003(平成15)年に建てられました。人頭税は、1637(寛永14)年から1903(明治36)年までの266年間課せられましたが、宮古島での先覚者の運動の盛り上がりと、県土地整理事業による新税法移行で廃止されました。
廃止から100年目の2003年、先人たちの苦労を後世に伝え、その歴史的意義を鑑み、記念碑が建てられました。 |
| ぬの |
布さらし浜*
 |
布さらし浜(ヌヌシャーパマ)は、西桟橋の北側に位置し、凸凹の少ない琉球石灰岩の海岸線が長々と続いています。
かつては、竹富島の伝統的な織物である芭蕉布を一昼夜ほど海水でさらす(これで色を定着させる)ことで知られた浜でした。(ヌヌシャーとは、布をさらすと言う意味です。)
布さらしする姿は竹富島を象徴する光景(原風景)だったのですが、残念なことに今では芭蕉布を織る人も減り、布さらしは稀になったそうです。今ではあまり布さらし浜と呼ばれることもなくなりました。
なお、2015年10月に約10年ぶりにこの布さらしが行われ、この生地で作った着物が、2015年の種子取祭に使われたそうです。
|
| ばぎ |
馬儀納屋(ばぎなや)
 |
泉屋の別館で、こぼし文庫の南側、新田観光の水牛車乗り場の東側にある馬儀納屋(ばぎなや)は、竹富島最古で唯一のカヤ葺きの家屋で、1866(慶応2)年に建てられたものです。2009年度末に修復されています。 |
| はや |
羽山会館

|
1995(平成7)年の7月に修復された仲筋集落の集会所が「羽山会館」です。 |
| へい |
平和の鐘
 |
竹富島の高那マツさんの85歳を祝賀してその息子達3人(大盛廣吉・高那三郎・大盛英信氏)らによって1974(昭和49)年に建立され、竹富公民館に贈られたものです。
梵鐘には、大盛英信氏のふる里への想いが刻まれています。
○梵鐘讃歌
この鐘の音が西塘の森から四方に鳴りわたるとき
すべての争いが止み 諸人の浄き平和の祈願が叶えられ
心に理解と融和と安らぎが生まれますように
夕げにおとずれ この鐘の音をきくとき 老たる身にも病める心にも
静かなよろこびが生まれますように
この島を往き来するすべての者が 安全で健やかで楽しい日々でありますように
そして この世に風と光と緑と人間が久遠にあるかぎり この島は栄え
平和と愛と敬母の梵鐘讃歌が鳴りわたりますように 合掌 |
| へり |
ヘリポート
 |
港から集落へ向かう道の途中の、右手側にあるヘリポートです。緊急時の対応として島には必要不可欠の施設です。 |
| ほう |
放送台
 |
「東の放送台」とも呼ばれますが、これは、竹富郵便局の西側にある高さ5mほどの石灰岩を積み上げたものです。
1951(昭和26)年8月28日に竣工したもので、「なごみの塔」よりも前に造られたものです。 |
| ぼう |
坊主墓*
 |
 |
坊主墓は、島北部を南北に縦断するミシャシ道と、東桟橋からカイジ浜間の外周道路の交差点から約15mほど西へ向かった北側の茂みの中(野原:ヌバル地区)にあります。
「坊主墓」は、お坊様が島に来るのが珍しかった時代、石垣島からお坊様が焼香に来ていたことに由来するそうです。一説によると坊主墓は、竹富島出身の西塘が25年間の首里での生活を終え、初の八重山統治者として、竹富に戻った際に連れてきた妾の墓だとも、妻の墓、母親の墓だとも言われていますが、詳細は不明です。墓は園比屋武御嶽の残り石で積み上げられているそうです。
墓石の上に据えられていた宝珠は、2009年の台風で二つに割れてしまいました。 |
| ほし |
星見石
 |
星見石は、かつて八重山において、農作業の時期を知るための星の観測に用いられていた石です。
八重山では時節を知るのに、星の観測、つまり「星見」が利用されており、観測の対象とした星(主に「昴:すばる」=プレアデス星団)が特定の時間に特定の位置に来ることを指標として、播種などの作業を行っていたと考えられています。 |
| まち |
待合所
てぇどぅんかりゆし館
 |
待合所からの眺め
 |
浮き桟橋の新設に併せて建設され、自動販売機や土産品店などがあります。離島ターミナルの中では最も充実していると言えるでしょう。 |
| みし |
ミシャシ海岸
 |
竹富島の北海岸で、かつては島の主要な港として利用されていました。
ガンキ(桟橋)跡のほか、アイヌソイ、イルヌソイといった小島などがあります。 |
| みー |
ミーナ井戸

|
昔から飲料水の確保に苦労していた竹富島には多くの井戸が残されています。
この「ミーナ井戸」は集落からアイアル浜へ行く途中にある井戸で、信仰の対象ともなっています。
下までは3m程度で、今でも水を湛えています。 |
| みろ |
彌勒奉安殿

|
彌勒奉安殿は、竹富島の最大の行事である「種子取祭」が行なわれる世持御嶽の東側にあり、五穀豊穣と幸福をもたらす「ミロク神」のお面が安置されている場所です。 |
| やえ |
八重山黒木の大木
 |
高級三線の棹等に使われる八重山黒木(ヤエヤマコクタン)の大木が、仲筋集落の前泊家にあります。
以前、この大木は売られ切り倒されることになったそうですが、いざ切り倒そうとすると、どこからともなく「切るな、切るな」との声がしたため、お金を持主に返して切るのを止めたそうです。キジムナーが住んでいるのかも? |
| やま |
山城善三先生顕彰碑
 |
 |
1948年初第の公選竹富町長となられ、また数々の偉業を称えられる山城善三先生の顕彰碑です。
この碑は西塘御嶽の斜め向かい側にあります。
銅像のそばには、『島人よ 西塘精神うけつぎて とわに栄えよ われ祈るなり』と記されています。 |
| ゆが |
ゆがふ館
(西表石垣国立公園
竹富島ビジターセンター)
 |
センター内入口
 |
竹富島の玄関口である東港近くに位置し、竹富島のフィールドミュージアムのインフォメーション施設です。西表石垣国立公園の竹富島の自然と伝統文化・芸能を紹介する施設として2004(平成16)年6月24日に開館しました。館名の「ゆがふ」とは、天からのご加護により豊穣を賜る「ゆがふ=世果報」の意味で、来島者と島民の間により良い交流が行われることを願って名付けられたものです。
NPOたきどぅんの運営施設で、八重山・竹富島の生活・歴史等について学ぶことができます。時間があれば、まずここで少し予備知識をつけて島内観光するのもよいかと思います。
・ 開館時間 8:00~17:00
・ 休館日:台風時
・ 入館料:無料
・ TEL:0980-85-2488 |
| よな |
與那國清介の碑

|
1901(明治34)年生まれで、竹富島の振興に多大な功績を残された「與那國清介」氏を称える碑です。 |
| よも |
世持御嶽*
 |
広場入口
 |
世持御嶽(ユームチオン)は王府時代の村番所で、竹富村誕生の1914(大正3)年から1938(昭和13)年まで村役場がありました。
火の神、農耕の神を祀る御嶽で、年中行事の各大祭が繰り広げられる場所です。中でも毎年旧暦の9月~10月に行われる竹富島最大の行事、種子取祭(たなどぅい)では2日間にわたり70演目余の多様な伝統芸能が奉納されます。種子取祭は国の重要無形民俗文化財に指定されています。
また、周囲は聖域として、昔からの森が残されています。 |
| んぶ |
ンブフル*
 |
仲筋集落の入り口にあるチャートの丘で、別名、ウシムル(牛丘)とも言います。
その昔、仲筋村を創始したアラシハナカサナリ(新志花重成)の下で牛を飼っていた男がいました。
ある日の深夜、牛舎から飛び出したその牛が角を突き上げ、一夜にして築き上げた丘と伝えられています。そして丘の頂上で「ンブフル、ンブフル」と大声で鳴いていたことから、このように名付けられたという伝説があります。
その一方でンブフルは倭寇の住居跡だという説もあります。 |
| んぶ |
ンブフル展望台
 |
竹富島全島が見渡せる、竹富島で一番高い場所がンブフル展望台です。ここは民家の屋上に鉄骨で組み上げて建てられたものです。
入場料100円(子供50円)は、セルフで展望台への階段横にある空き缶に入れるようになっています。 |